
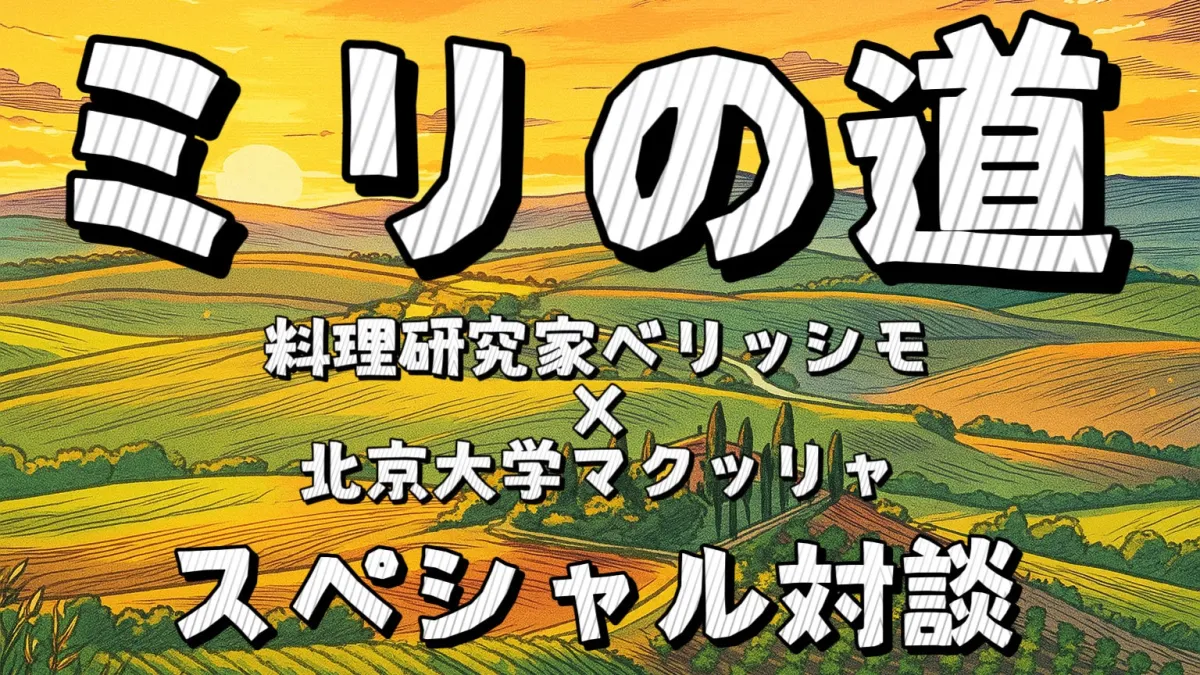
科学と料理の新たな交差点『1ミリ対話』が示す未来の食文化
科学と料理の新たな交差点『1ミリ対話』が示す未来の食文化
2025年10月26日、株式会社ビリオネア主催のオンラインイベント「ミリの道 科学と料理が出会う1ミリの対話」が開催されました。このイベントは、料理研究家、タレント、俳優、ファッションインフルエンサー、実業家としても活躍するベリッシモ・フランチェスコ氏と、北京大学の准教授で物理学者のダニエーレ・マクッリャ氏によるもので、科学と料理の出会いを探る貴重な機会となりました。
複数の言語で交わされる対話
参加者は日本語、イタリア語、英語を通じて、持続可能性や倫理、文化、そして人間らしさについて深く掘り下げることができました。「計る」という行為が、単なる調理技術を超えて、私たちの環境や文化的責任にどのように関わるのかが議論されました。
料理や科学における「計る」という行為が最近注目を集めています。これは単なる技術だけではなく、環境への配慮や文化的責任を伝える重要な要素として位置づけられています。たとえば、食材選びや調理方法のなかでの微細な違いが、地球に与える影響や未来の食文化にどのように結びつくのかが具体的に示されました。
国連食糧農業機関(FAO)の2024年統計年鑑は、食料システムの持続可能性が食料安全保障の重要な要素であると指摘しています。この研究結果は、料理のプロセスでの「わずかな差」が食品ロスや環境への負担軽減につながることを示唆しています。さらに、ミラノ工科大学の研究によれば、「計る」意識を向上させれば、食品ロスが最大30%削減できるかもしれないとのことです。
小さな違いが生む大きな意味
しかし、グローバル化や大量生産の影響で、日々の料理や科学の現場では「効率」が優先され、時には感覚や責任が見えにくくなってしまいます。便利な調理機器の普及によって、食材との対話が減少したり、文化の奥深さが失われる危険性もあります。
幸いにも、日常の小さな選択が気候中立な社会を実現する一歩になると強調されている研究もあります。たとえば、料理の火加減や食材の選択は、「計る」意識を高めることで、持続可能な未来に向けた重要な鍵となり得ます。
イベントで語られた「1ミリ」の重要性
1ミリの感覚は、味覚や心に新しい調和をもたらします。このイベントでは、そばとオリーブオイルを通じて、五感全てを刺激する感覚が引き出されました。具体的には、天ぷらの揚げ加減やパスタのアルデンテ、味噌の発酵時間など、1ミリの違いが素材への敬意と環境への責任を形づくることが強調されました。
ベリッシモ氏の視点
「料理は“たった1ミリ”で変わります。小さな違いが、美味しさだけでなく、地球への思いやりに繋がります。」とベリッシモ氏は語ります。味噌を溶かす際の火加減や、パスタの茹で時間など、細かな配慮が食文化の将来を支える鍵であると力説しました。
マクッリャ氏の視点
続けてマクッリャ氏も、「その1ミリには、見過ごされがちな秤がある。静けさの中で、それは世界の呼吸をそっと測っています。」と述べ、知覚することの重要性を強調しました。
まとめ
このように、『1ミリ対話』は科学と料理を結びつけた新たな試みであり、持続可能性や倫理についての重要な対話を促進する場として意義深いものでした。料理の背後にある文化的背景や科学的根拠を理解することで、より深い食文化への理解が広がります。これからの食文化の未来を共に考えるきっかけになることでしょう。そして、参加者に感銘を与えたこの対話が、SNS上での感想を通じて、より多くの人々に広がっていくことを願っています。
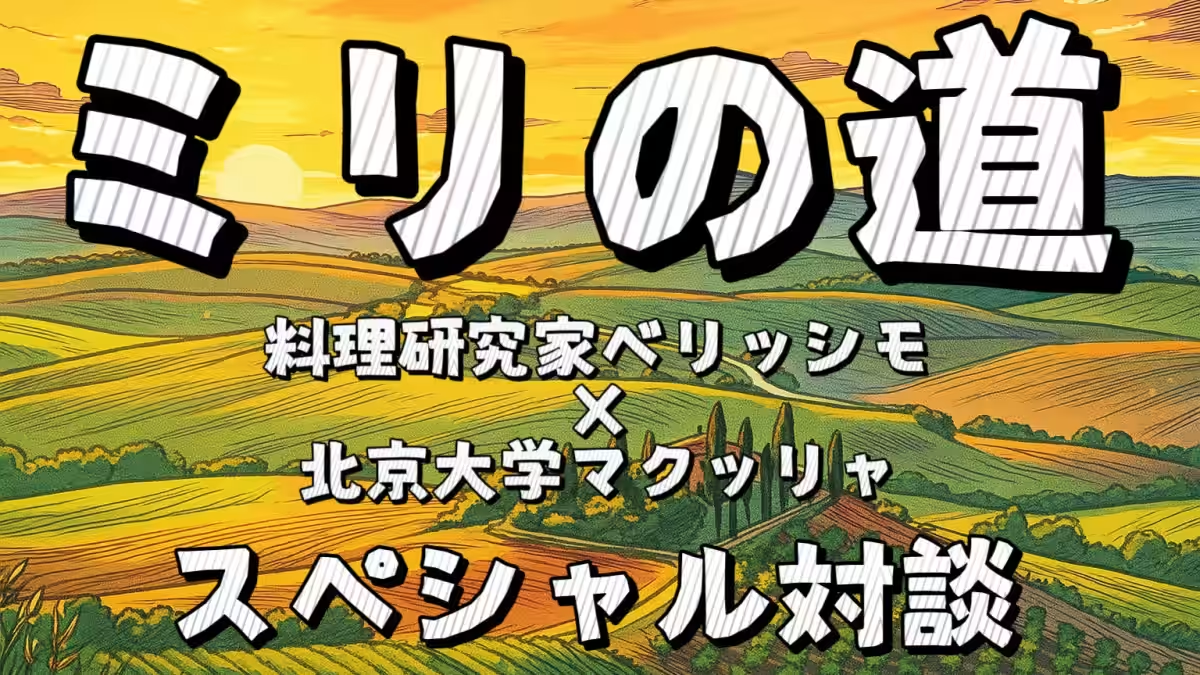


トピックス(ライフスタイル・カルチャー)


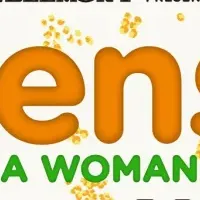
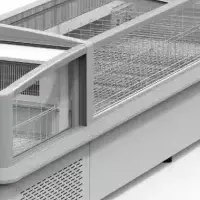
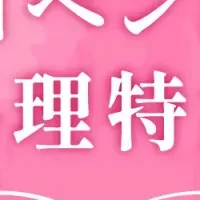


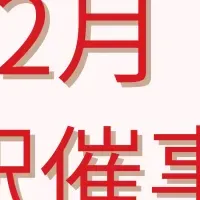


【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。