

国産小麦のパン作りがもたらす未来を子どもたちに伝えよう
国産小麦のパン作りが示す新しい未来
国産小麦のパン作りに挑戦するパルシステム生活協同組合連合会。本部は新宿区大久保にあり、理事長は渋澤温之氏。彼らは、食料自給率向上を掲げ、特に小中学生向けに『おしごと年鑑』を通じて、このパン作りの重要性を紹介しています。
食を支える国産小麦の重要性
国産小麦の使用が進む背景には、国内生産者を応援するという明確な目的があります。『おしごと年鑑』では、「日本で育てた『国産小麦』のパン作りにこだわる理由」をテーマにした記事が掲載され、子供たちが日々の食を通じて理解を深める助けとなっています。
特に、国産小麦にはうどんなどに適した品種の傾向があり、パン作りには挑戦が伴います。盤ブレッドは、2019年から製粉会社と共に研究を重ね、異なる小麦の配合を工夫して安定したパン生地の製造に成功しました。これにより、彼らは約140種類のパンを生産し、2025年度には国産小麦の使用比率が90%に達することを目指しています。
持続可能な地域づくりと食育の重要性
パルシステムは、国産原料や産直原料を使用することで、生産地域の生活を守りながら新鮮で楽しい食品を消費者に提供しています。利用者自身が食の背景を理解することで、どのようにして食が作られているのかを知る良い機会となるのです。
また、同団体は『おしごと年鑑』を通じて、毎年全国の小中学校に教材を寄贈し、子どもたちに「働くこと」を楽しく学んでもらう機会を提供しています。このような活動は、子どもたちが未来の職業について考えるきっかけとなります。
パルシステムの支援により、環境を考慮した米や有機野菜の生産過程についても知識を深められ、学校では教科書だけでは学べない食育の情報が得られます。子どもたちに日常の食文化に興味を持たせるきっかけを与えることが、長い目で見れば地域や国家の食料自給率向上に寄与することになります。
結びとして
『おしごと年鑑』やパルシステムの取り組みは、食を介して子どもたちが未来を描き、豊かな地域づくりに貢献するための重要な一歩となります。季節ごとの味わい、地域の特産品、そして国産小麦のパンが、私たちの日々の食卓にどのように寄与しているのかを考える良い機会でもあります。このような取り組みを通じて、私たちの未来がどのように変わっていくのか、楽しみですね。




トピックス(ライフスタイル・カルチャー)


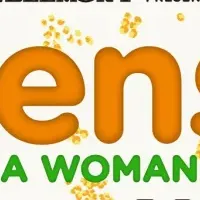
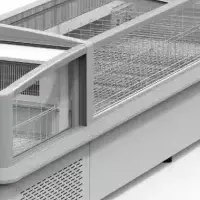
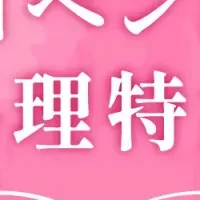


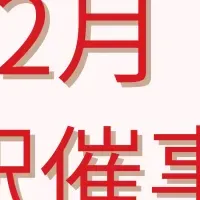


【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。