
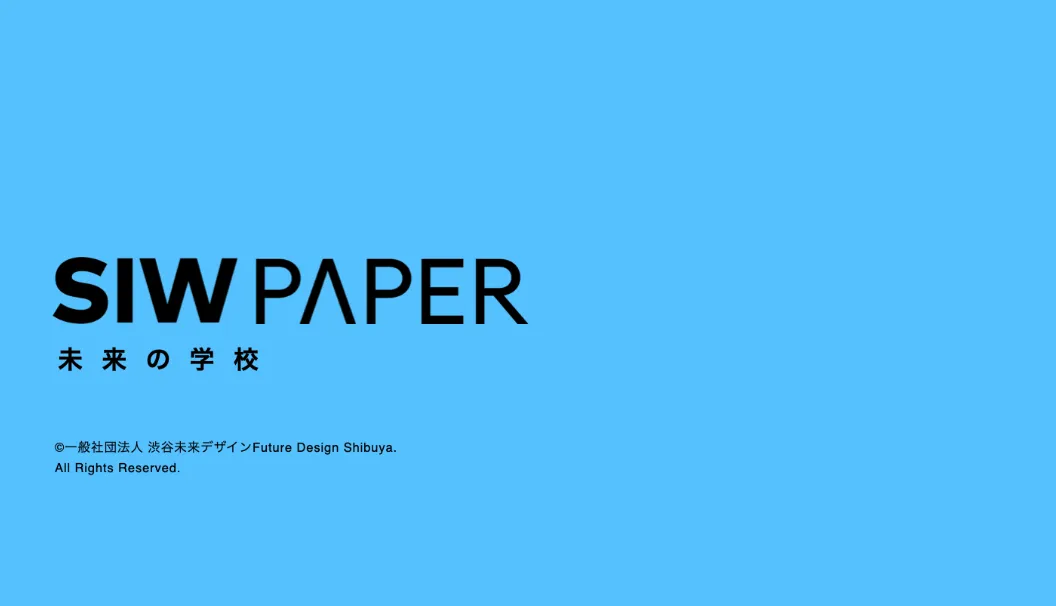
渋谷が描く未来の学校。テクノロジーと探究学習で新しい学びを実現
渋谷が描く未来の学校
渋谷の教育が新たな方向性を示す「未来の学校」ホワイトペーパーが公開されました。この報告書は、社会の変化を背景に、教育の在り方を再考し、次世代の学びを共創するための課題と提言を取りまとめたものです。特に注目されるのは、テクノロジーの活用と地域との連携がどのように教育に新風を吹き込むのかという点です。
「未来の学校」構想の背景
少子高齢化やテクノロジーの進化、創造的人材の育成といった課題に直面する現代の日本。渋谷区では特に、新たな教育プログラム「シブヤ未来科・探究学習」の導入を進めています。このプログラムは、地域や企業と協力し、学校を「未来社会を創る場」と位置づけ、児童・生徒が主体的に学ぶ環境作りに取り組んでいます。
「未来の学校」構想では、体験を重視した探究学習の実施が奨励され、具体的にはヤマハの「ボーカロイド教育版」とNHK関連企業のロボットプログラミングなど、多様な学びが用意されています。
具体的な取り組みと成果
- - 体験型学習の推進: ヤマハが開発した「ボーカロイド教育版」を使った音楽・プログラミング体験で、子どもたちの表現力を育む試みが行われました。また、NHK関連企業によるロボットプログラミングも実施され、多様な体験を通じて創造性を引き出しています。
- - 継続的な対話の実現: 教育現場との意見交換を重視し、学校の運用可能性や子どもたちのニーズを直接反映した提言を行っています。中学校の教員や教育委員会との協議を通じて、学習環境の改善を進めています。
提言内容
提言の中心には、学校が地域社会とつながる「共創拠点」としての役割が掲げられています。そのための施策として、主体的に学ぶ環境の整備や教科を超えた横断的な授業の実施が重要とされています。
さらに、「学び」を社会や地域、テクノロジーとつなげる仕組みづくりが求められており、評価方法の見直しやインフラ整備が急務です。
今後の展望
「未来の学校」づくりは単なる教育プログラムの刷新にとどまらず、学校を中心に新たな社会のエコシステムを築く試みです。渋谷での取り組みが他地域や国際的な教育改革に影響を与えることを目指し、今後も提言の実装に向けた努力が続けられます。
まとめ
教育の未来を考える上で、「未来の学校」ホワイトペーパーは極めて重要な資料となります。テクノロジーを駆使した新たな探究学習の場は、未来の子どもたちに必要なスキルを提供するだけでなく、社会と深くつながる機会をも与えるでしょう。私たちもこの動きに注目し、教育の可能性を広げる活動に参加していきたいですね。
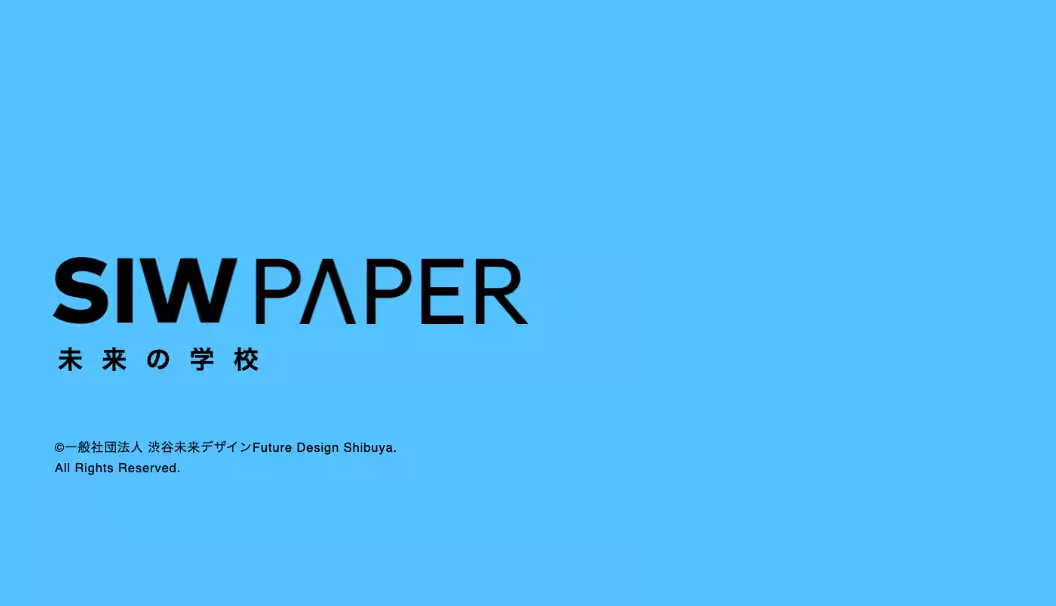


トピックス(ライフスタイル・カルチャー)


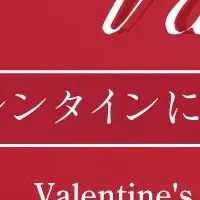
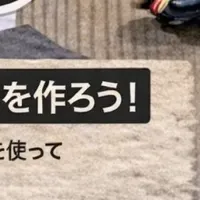
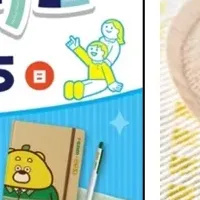
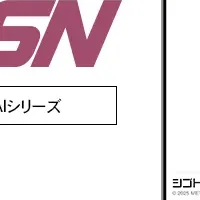
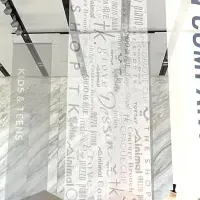

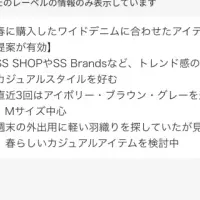

【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。