

サステナブルな水産業を目指す新しい給餌システムの試験開始
サステナブルな水産業を目指して
日本の海洋資源が危機に瀕している中、新たなテクノロジーによるアプローチが求められています。株式会社FOOD & LIFE COMPANIES(以下、F&LC)、尾鷲物産株式会社(以下、尾鷲物産)、そしてヤンマーホールディングス株式会社(以下、ヤンマーHD)の3社が協力し、サステナブルな養殖業の実現を目指す「遠隔自動給餌システム」の実証試験を2025年6月から開始します。
養殖業の現状と課題
近年、天然資源への依存を減らすため、養殖業の重要性が増しています。しかし、養殖業界は人手不足や給餌コストの上昇、さらには夏季の海水温の上昇による漁獲量に影響を受けています。これらの課題を解決するため、革新的な給餌技術が必要とされています。
遠隔自動給餌システムの特徴
今回開発された遠隔自動給餌システムは、海水と餌を混合して供給する技術を取り入れています。このシステムは、将来的に沈下式生簀への適用も見据えて設計されています。三重県尾鷲市に位置する尾鷲物産のブリ養殖場では、年間約60万尾を生産していますが、今回の実証試験では約14,000尾を対象に、海面生簀でのテストが行われます。
共同実証試験の内容
この共同実証試験は、以下のように進行します:
- - 実証場所:尾鷲物産株式会社尾鷲養殖場(三重県尾鷲市)
- - 予定期間:2025年6月から2026年1月(予定)
- - 対象魚:ブリ約14,000尾
各社の役割は次の通りです:
- - F&LCは養殖ブリの品質評価を担当。
- - 尾鷲物産は養殖場の提供とブリの育成を行います。
- - ヤンマーHDは、給餌システムの開発と運用、実証データの収集・分析を実施します。
この実証試験により、F&LCは「変えよう、毎日の美味しさを。広めよう、世界に喜びを。」というビジョンのもとで、持続可能な水産物の調達を目指します。尾鷲物産は、地域の環境に適した養殖技術を確立し、ヤンマーは「食の恵みを安心して享受できる社会」を目指しています。
先進技術の導入
ヤンマーグループは、専用の水中カメラを用いて魚影をデータ化し、画像認識技術で魚の数や体重を計測する技術を開発。また、遠隔地から複数の生簀を一望できる人間工学に基づいた画面(HMI)を採用し、このシステムにより、給餌が効率的に行えます。これにより、従来の手法よりも作業量が軽減され、社会情勢による餌代の高騰にも対処することが期待されます。
今後の展望
本実証試験の結果、得られた技術やデータは、2026年中にF&LCが運営するスシローの店舗で販売されるブリに活用される予定です。サステナブルな水産業を支える新しい取り組みが、未来の食卓に美味しい魚をお届けする手助けになることを期待しています。
持続可能な魚の供給と養殖業の発展に向けたこの試験が、他の養殖業者への波及効果をもたらすことに期待が寄せられています。




トピックス(ライフスタイル・カルチャー)

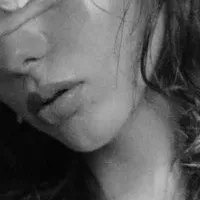


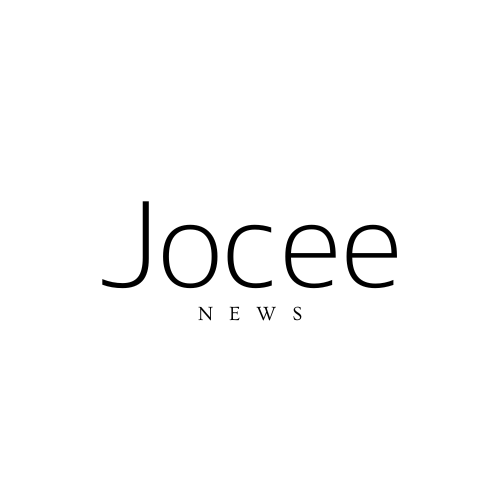
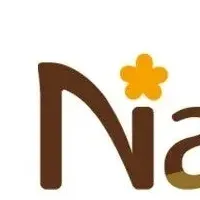
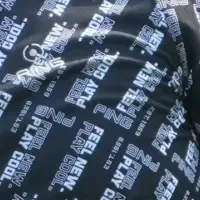

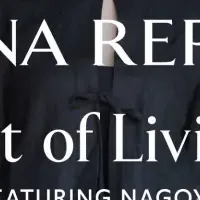

【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。