

食品ロス削減に向けた業界の商慣習変更の重要性と新たな取り組み
食品ロス削減に向けた業界の商慣習変更の重要性
10月30日は、毎年恒例の『全国一斉商慣習見直しの日』として、食品ロス削減に向けた大きな意義が注目されています。公益財団法人流通経済研究所が設置した「食品ロス削減のための商慣習検討ワーキングチーム」が、これまでの取り組みの成果や今後の方針について報告しました。食品ロス問題は、私たちの生活に直結する重要なテーマでもあり、今回はその最新の状況をご紹介します。
調査概要と背景
このワーキングチームは、農林水産省と公益財団法人流通経済研究所が連携して活動しています。食品ロスは過剰在庫や返品などさまざまな要因で発生しており、これを解決するには食品メーカー、卸売業、小売業が協力して取り組むことが重要です。2025年に向けた調査では、560社を対象に商慣習の見直しの活動を調査し、業界の取り組みを社会に広めることが目的とされています。
調査結果のハイライト
主要な取り組み
調査によると、食品メーカーにおける「賞味期限の延長」への取り組みが393社に達し、小売業でも「納品期限の緩和」が377社に広がりました。このような業者間の相互依存は、商慣習の見直しが進む大きな要因となっています。特に、賞味期限を延長することで、商品の消費期間が長くなり、結果的に食品ロスの削減にもつながると言われています。
新たな施策
また、フードバンクへの食品寄贈や販売期限延長の取り組みが進行中で、物流改善に向けた努力も続いています。特に、「てまえどり」という購買行動を促進することで、消費者自身が食品ロス削減に参加できる体制が整いつつあります。これは、消費者側と企業側がウィンウィンの関係を築く良い例となるでしょう。
課題と今後の方向性
ただし、業界全体で商慣習の改善に向けた努力は引き続き必要です。今回は、販売期限の延長を行う小売業者が多く見込まれ、業界全体で「納品期限の緩和」がさらに促進されていく見込みです。これにより、さらなる食品ロス削減が図られることが期待されます。
取り組み事業者の公表
また、取り組み事業者名が公式サイトにて発表されます。これにより、消費者は積極的に食品ロス削減に加わる企業を応援することができます。企業の取り組みを知ることができれば、私たちも日常生活での選択肢を変えていくきっかけになるでしょう。
食品ロス削減の重要性
このように、食品ロス削減は企業単独での取り組みではなく、私たち消費者にも密接に関わっている問題です。業界の取り組みを支持し、自分たちの日常生活の中でも食品ロスについて意識して行動することが求められています。今後も社会全体でこの問題に取り組む意義と重要性を再認識し、持続可能な食の未来を築いていきましょう。



トピックス(その他)



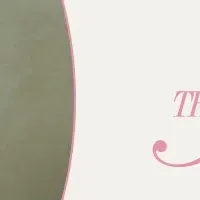
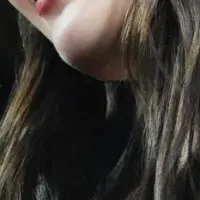

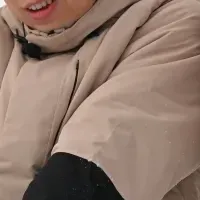

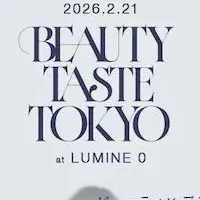
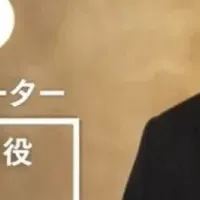
【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。