

道東カーボンファーミング研究会が描く新しい農業の未来とは?
道東カーボンファーミング研究会が描く新しい農業の未来とは?
2023年8月に設立された道東カーボンファーミング研究会は、北海道別海町を中心に、持続可能な農業の実現に向けた研究を行っています。2025年度の活動報告では、異なる規模の酪農モデルに対応した3つの実証事例を通じて、各農場の取り組みを紹介し、持続可能な農業の未来を模索しています。
1. 大規模農場の試み:中山牧場
大規模な酪農を展開する中山牧場では、1,300頭の乳牛を飼育し、バイオガス発電を行っています。ここでは、牛の糞尿をエネルギー源として利用し、資源循環型の農業を実践中です。特に、不耕起圃場での堆肥や消化液を用いた炭素貯留の調査を進めており、農業の在り方を見直すことが求められています。中山勝志会長は、「資源循環を意識して、酪農の可能性を追求したい」と語ります。
2. 中規模農場の挑戦:リジッドファームズ
北海道野付郡に位置するリジッドファームズは、乳牛100〜300頭を飼育している新しい参加者です。彼らは有機JASを取得した経験を持ち、この実証では化学肥料を使用した区とスラリーを散布する区に分け、比較調査を行っています。代表の森田哲司氏は、「中規模農家は多くの課題を抱えており、サステナブルな農業と高品質な飼料生産の両立が求められる」と述べています。
3. 小規模農場の取り組み:養老牛山本牧場
養老牛山本牧場は、約30頭の乳牛を完全放牧で飼育しており、カバークロップによる土壌改善を目指しています。2025年度は、播種の種類を増やし、牧草地でのカバークロップの定着を図る計画です。山本照二代表は、「土の生き返りを促すために様々な植物を播き、小さな牧場でも持続可能な農業を実現したい」と意気込みを見せています。
土壌健康度調査の実施
2025年10月には、3年目となる土壌健康度調査が実施されます。圃場を試験区に分け、それぞれ異なる施肥方法を採用し土壌の変化を観察。これにより、さまざまな農法の効果を測定する計画です。特に、春から秋にかけての炭素貯留量や微生物総量の調査結果は、2026年2月頃に発表される予定です。
次世代を担う人材育成
新たに高校生や大学生を対象にした教育プログラムもスタートしました。「土壌が温室効果ガスを貯留する仕組み」や「持続可能な酪農の循環構造」を学ぶ機会を提供し、次世代のサステナブルな農業推進者を育てています。特に、私立新渡戸文化高等学校のスタディツアーが行われ、実際の現場での実習を通じて探究学習が行われました。
カーボンファーマーの活動を発信
道東カーボンファーミング研究会では、カーボンファームに取り組む酪農家の活動を伝える「note」を立ち上げ、様々な情報を発信しています。新たなカーボンファーミングを志す酪農家や乳業関係者に向けて、持続可能な農業の重要性を広めるべく努めています。
このように、道東カーボンファーミング研究会は、地域の特色を活かしながら、未来の持続可能な農業を実現するための取り組みを進めています。今後も彼らの活動から目が離せません。


関連リンク
サードペディア百科事典: 道東カーボンファーミング サステナブル農業 酪農モデル
トピックス(ライフスタイル・カルチャー)

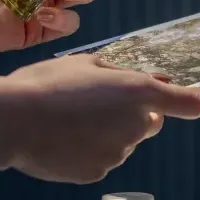





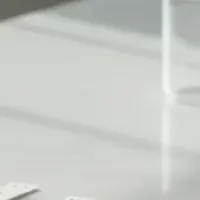


【記事の利用について】
タイトルと記事文章は、記事のあるページにリンクを張っていただければ、無料で利用できます。
※画像は、利用できませんのでご注意ください。
【リンクついて】
リンクフリーです。